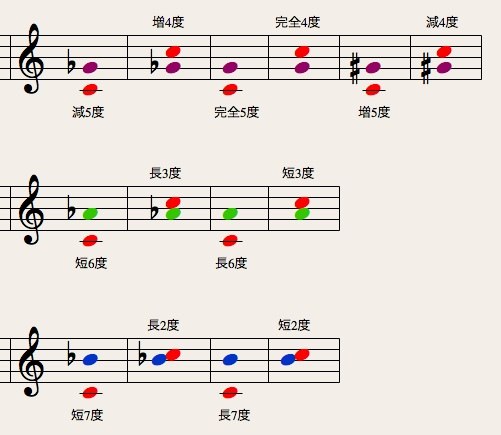2つの音の高さの隔たりが「音程」です
音程は「度」という単位で示されます
下の画像では、片方がCの場合を例にしてありますが
解説を参考にして
どんな音同士でも音程が判るようになって下さい
これは「コード」を理解する為に必要です
2つの音の高さの隔たりが「音程」です
音程は「度」という単位で示されます
下の画像では、片方がCの場合を例にしてありますが
解説を参考にして
どんな音同士でも音程が判るようになって下さい
これは「コード」を理解する為に必要です
同じ高さの音は「完全1度」です
半音は「短2度」
全音は「長2度」
3半音=全音+半音で「短3度」
4半音=全音2つ分(ドとミの関係)が「長3度」
2つの音のうち
上の音を1オクターブ下げる、または
下の音を1オクターブ上げる、事を
「転回」
と呼びます
元の音程を「原音程」
転回された音程は「転回音程」
です
原音程と転回音程には、下記のような関係があります
原音程の度数+転回音程の度数 = 9
そして
長短、増減は
原音程と転回音程では逆になる
(完全は完全のまま)
例
Dの長6度上は
9-6=3
長 → 短となって
短3度下の音と同じ音名
全音+半音下なので・・レドシ
B です
Eの完全5度下は
9-5=4
完全 → 完全のまま
完全4度上の音と同じ音名
A です
•Cから完全4度上ならば、C D E F と辿ります。EとFの間が半音、他は全音なので、Cの完全4度上はF
•Bから完全4度下ならば、B A G F と下に向かって辿ってF・・ですが、この中には半音がないので、B〜F間の音程は増4度です。完全4度は、Fを半音上げた = 間隔を詰めたとイメージする = F#(G♭)
「完全5度」も同様に、音名を5つ辿ります
•Cから完全5度上ならば、C D E F G と辿ります。EとFの間が半音、他は全音なので、Cの完全5度上はG
•Fから完全5度下ならば、F E D C B と下に向かって辿りますが、FとEに加え、CとBも半音なので、F〜B間の音程は減5度です。Bをさらに半音下げた = 間隔を広げたとイメージする = B♭(A#)
さて
6度以上離れた音程は
次に説明する
「転回音程」
から簡単に見つけられるので
とりあえず、どの音からでも
2度、3度、4度、5度、上下
が判るようになって下さい
ここまでは、多くても半音4つ分なので判りやすいと思いますが
4度音程は次のように考えると良いでしょう
音名を4つ辿ってみて
その中に半音の関係が1つだけあれば「完全4度」
5度音程も同様に
音名を5つ辿ってみて
その中に半音の関係が1つだけあれば「完全5度」
#や♭が付く音からは、その半音上下から探せば良いでしょう
増4度と減5度、増5度と短6度、は同じ音程ですが
どちらの呼び方をするかは、状況によって変わります
これも、もう少し先、コードの説明に回します